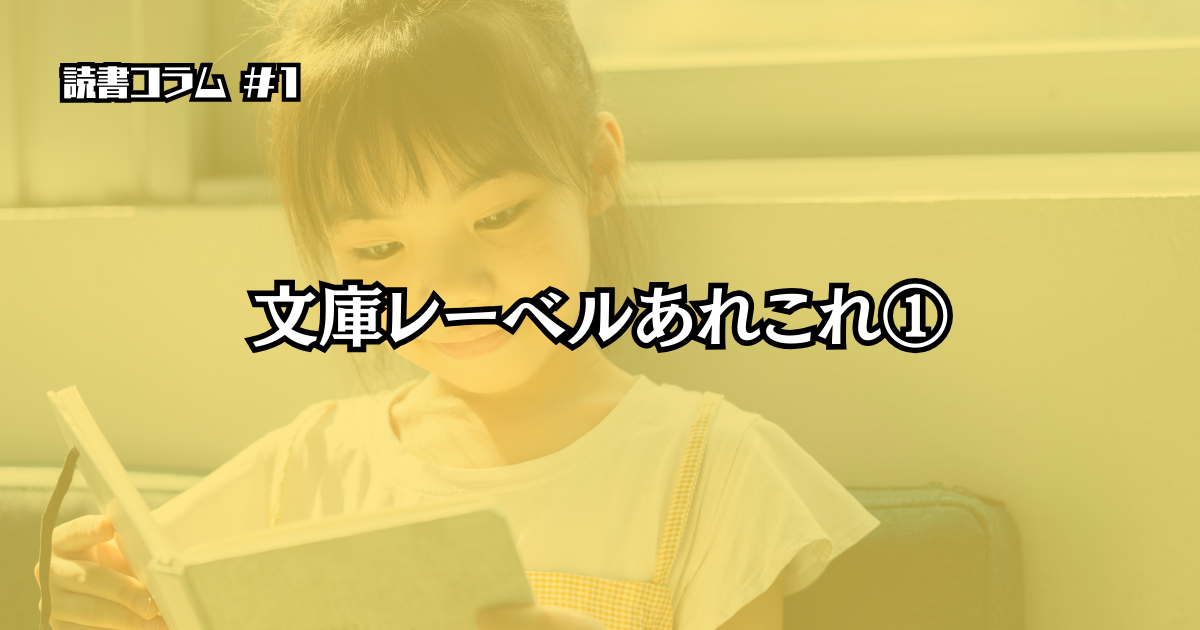ページの隙間から失礼します。てるまれです。
記念すべきコラム第1回は、私がよく読む文庫レーベルのあれこれをお話ししようと思います。
はじめに
これを読んでいる読書家さんにも、きっと印象に残っている出版社やレーベルがあると思います。
紙の質感、フォントの見やすさ、取り扱っている作品など、誰しも読書好きであれば好きな本の出版社、もしくはレーベルを覚えているものではないでしょうか?
今回は、私の印象に残っている文庫本を出しているレーベルを3つほど取り上げてご紹介します。
文庫レーベルあれこれ
新潮文庫
新潮文庫は1914年に創刊した老舗レーベル。
文学作品は国内作品から海外作品まで幅広く扱う脅威のラインナップ。読書好きなら手に取った方も多いはず。
このレーベルは私の読書ライフの起源にして頂点。
敬愛する恩田陸先生の『夜のピクニック』を読んでいなかったら、きっとこの記事も書いていないと思います。
フォントや文字の大きさ、文字・行間の空白など、好きなポイントを挙げればキリがないのですが、私が一番気に入っているのは、なんといってもその紙質です。
新潮文庫の紙質は、上質で薄く、ほんのり赤味のあるクリーム色。
紙の地色が白すぎると、文字の墨色(黒色)とのコントラストがつきすぎて、長時間読むと疲れてしまいます。
おそらくそういった点を考慮し、若干の赤色を混ぜ、目に優しくしてくれているのでしょう。
スピン(栞)が付いているのもポイントで、これが嬉しいという声もよく聞きます。
私はいつも革紐の栞がついているブックカバーを愛用しているので、外出時に使う機会はほとんどありませんが、いいなと思った描写や台詞のページに挟んでおいて、本棚に閉まっておくのがマイブーム。
その場面だけパラっと読み返したい時に、とても重宝する使い方です。
読書慣れしていない知人にオススメの本を挙げる時も、新潮文庫の本が多い気がします。
 てるまれ
てるまれちなみに”におい”も好き。古めかしさの中に微かな神秘性が宿っているというか——これは私がブックオフなどで中古本を買うことが多いからかな?
ポプラ文庫
2020年にリニューアルしたポプラ文庫。
しかし、私が読書沼にハマったのは社会人になってからだったこともあり、実は最近まで読んだことがないレーベルだったんですよね(汗)
最初に読んだ作品は夏木志朋先生の『二木先生』だったか、辻村深月先生の『かがみの孤城』だったか……。店頭でぱらぱらめくったのも含めると、初めての出会いはそのどちらでもなかったかもしれませんが……。
いずれにせよ、ポプラ文庫の本を開いた時に思ったことはよく覚えています。
「ん? 文字がなんか……変!?」
そう。文字に違和感を持ったのです。
丸みを帯びているというか、若干横に広いというか——とにかくこれまで読んできた文庫本と何かが違う!
ですが、そんな困惑も束の間。読みはじめは違和感しかなかったものの、読み進めていくうちにいつの間にか慣れていき、文字の方から吸い付いてくるようでした。
調べたところ、このフォントは「UD黎ミン」というものらしく、ユニバーサルなデザインが特徴みたいです。
言われてみるとたしかになんだか読みやすい。けれど読み心地は新鮮という、不思議な読書体験ができました。



気になった方は、ぜひ一度ポプラ文庫を手に取ってみてください。私が何を言っているのか、なんとなく理解できるかと思います。
ハヤカワ文庫
さて、遂にきましたハヤカワ文庫。
このレーベルの「ある話」を語るべく、本コラムを書いていると言っても過言ではありません。
とにもかくにも、ハヤカワ文庫といえば独自のサイズである「トールサイズ」でしょう。
文庫本のサイズは、一般的にA6判(14.8cm×10.5cm)。スーツやコートのポケットにも入るくらいの大きさで、単行本や新書よりもコンパクトなことが特徴です。
しかし、ハヤカワ文庫のサイズは15.7cm×10.6cm。正面から見た時の横幅はほぼA6判と変わりませんが、縦が1cmほど長いのです。
1cm。たった1cm。
この1cmは、多くの読書家を悩ませてきました(多分ね)。
そうです! A6判サイズのブックカバーに対応していないことがほとんどなのです!
これは由々しき事態です。私のような、外出先ではブックカバーを付けたい人にとっては、特に。
ちなみに本棚に収納した際、他の文庫本と高さが合わない——つまり、見栄えが悪くなるという声も耳にしました。
私は本を作者ごとではなく、出版社ごとに分けて本棚に収納しているのであまり気にならないのですが、その気持ちは理解できます。
と、ここまで散々なことを書いてきましたが、出版元である早川書房が「読みやすいサイズ」と謳っているだけあって、本そのもののリーダビリティはとても高いです。
ミステリーやSFの海外作品も多く取り扱っており、解説含めてどれも質の高いものばかり。
もともと私はSF小説に苦手意識を持っていたのですが、ハヤカワSF文庫から刊行されている、伴名練先生の『なめらかな世界と、その敵』を読み、SFの世界に一歩を踏み出しました。
この作品についても語りたいことがたくさんあるのですが、それはまた今度の機会に。
ハヤカワトールサイズ用のブックカバーが販売されているのもちらほら見かけますし、昔から愛読している人にとっては、もうすっかり定着しているんでしょうね。



ハヤカワ文庫ブックカバー問題に悩んでいる人は、これを機に思い切ってブックカバーをひとつ増やしてみるのもアリかもしれません。
おわりに
コラム第1回ということで、程度が分からずほとんど殴り書きに近いものをお届けしてしまいました(汗)
機会があれば他にも私が愛読している新潮文庫nexやPHP文庫、実業之日本社文庫などにも触れてみたいですね。
それでは今回はこの辺りでお暇といたします。
ご一読いただき、ありがとうございました。